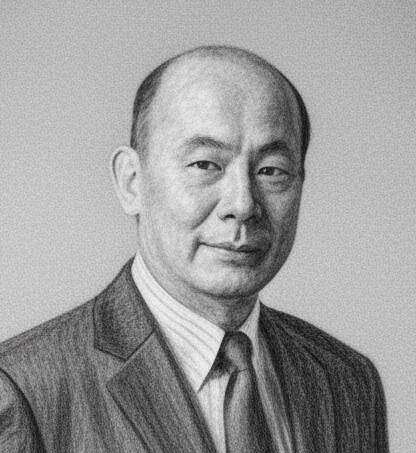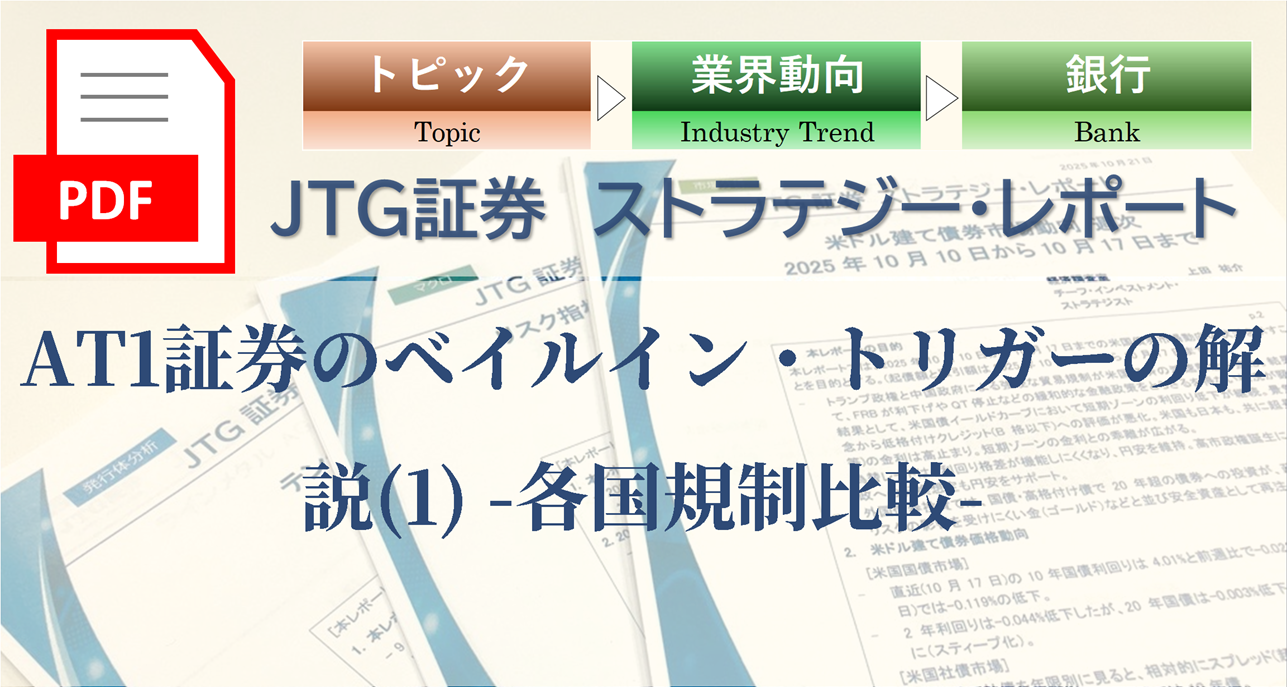バーゼル3とは?銀行規制の基本をわかりやすく解説
バーゼル3銀行規制は、2007〜2009年の世界金融危機(リーマン・ショック)を教訓として導入された国際的な銀行規制の枠組みです。債券投資においても、銀行規制により作られた様々な資本性証券が銀行から発行され、多くの投資機会を提供してきました。ここでは、バーゼルIII規制の概要をご紹介します。
1. 導入の背景と目的
バーゼル3規制は、2007〜2009年の世界金融危機(リーマン・ショック)を教訓として導入された国際的な銀行規制の枠組みです。
危機では、多くの銀行が十分な自己資本や流動性を持たず、また過度にレバレッジをかけた状態でリスクを取っていたことが判明しました。これにより、信用不安が連鎖的に広がり、金融システム全体が不安定化しました。
この経験から、銀行の自己資本をより強固にすること、過剰なリスクテイクを抑制すること、流動性リスク管理を厳格化することが急務とされ、従来の「バーゼルII」を大幅に改訂した「バーゼルIII」が2010年に発表されました。バーゼルIII銀行規制とは、世界金融危機を教訓に策定された国際的な銀行監督基準であり、銀行が十分な資本と流動性を保持し、過度なリスクテイクを抑制し、かつ透明性を確保することを目的としています。
その目的は大きく3点に集約されます。
1.透明性と市場規律を高め、監督当局や投資家がリスクを早期に把握できる仕組みを整える。
2.銀行の自己資本の質と量を強化し、損失吸収力を高める。
3.過度なレバレッジや短期資金依存を抑制し、健全なバランスシートを確保する。
2. 規制を策定・運用する主体
バーゼルIII規制を策定したのは、バーゼル銀行監督委員会(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)です。ただし、バーゼルIII規制は「国際合意」であるものの、実際に拘束力のある規制を定めるのは各国の金融監督当局です。現地の法律や規制を定め、それぞれが一定の調整を行って制度化を行うため、細かい銀行規制の内容は、各国・各地域で異なります。
- BCBSとは
- 1974年、国際決済銀行(BIS)のもとで設立。
- メンバーは主要国の中央銀行・金融監督当局(日本からは日本銀行と金融庁)。
- 法的拘束力を持つ「国際条約」ではなく、各国が合意した「国際基準」を提示する役割を果たします。
バーゼルIII合意を銀行への監督業務に反映させるため、各国・各地域では、自国の法制に反映させた独自のルールを定めました。以下に、その例を示しました。
- 欧州:EU規則(CRR/CRD)として実装。
- 米国:FRB、OCC、FDICが規制を導入。
- 日本:金融庁が自己資本比率規制や流動性規制として告示。
3. バーゼルIIIの役割と仕組み
バーゼルIII規制は「三つの柱(Three Pillars)」からなる構造でできています。
(1) 第一の柱(最低資本・流動性規制)
- 自己資本比率の最低基準を強化(CET1比率4.5%以上など)。
- レバレッジ比率の導入(最低3%)。
- 流動性規制(LCRとNSFR)の導入。
- マクロプルーデンス要素(資本保全バッファ、カウンターシクリカル・バッファ、G-SIB追加資本)。
(2) 第二の柱(監督当局による審査と介入)
- ICAAP(内部資本評価)、ILAAP(流動性評価)の提出を銀行に義務付け。
- 当局はSREP(監督審査プロセス)を通じて追加資本(Pillar 2 Requirement)を課す。
(3) 第三の柱(市場規律とディスクロージャー)
- 開示の標準化(KM1, OV1, CC1/2, LR2, LIQ1/2など)。
- 投資家や預金者が銀行のリスク状況を把握しやすくすることで、市場による懲罰的規律を促す。
これらの柱の詳細な内容は、別の記事で説明します。
4. バーゼルIIIの主要な規制内容
バーゼルIIIに従って、各銀行に適用される規制には、下記のようなものがあります。
(1) 自己資本の質と量の強化
- 核心的自己資本(CET1)を厚くし、従来よりも「損失吸収力の高い資本(普通株式など)」を中心に据える。
- ハイブリッド証券や劣後債はTier2に限定。
(2) レバレッジ比率
- 資産規模に対して資本をどれだけ持っているかを単純に測る指標。
- リスク加重を使わないため、モデル裁量に依存せず、透明性が高い。
(3) 流動性規制
- LCR:30日間の資金流出をカバーできる高品質流動資産を100%以上保有。
- NSFR:長期的に安定した資金調達比率を100%以上維持。
(4) マクロプルーデンス規制
- 資本保全バッファ:一律2.5%追加。
- カウンターシクリカル・バッファ:景気過熱時に追加資本を課す。
- G-SIB追加資本:国際的にシステム上重要な銀行に対して課す。
(5) TLAC(総損失吸収力)
- 特にG-SIBを対象に、破綻時に債権者負担で自己再建できるよう資本+負債の下限を規定。
5. バーゼルIIIの導入スケジュール
バーゼルIII規制は、複数の段階を経て導入・適用されました。以下に、導入からの流れを時系列で示しました。規制の最終化は2028年まで続く形となっています。
- 2010年12月:バーゼルIII合意。
- 2013〜2019年:資本比率強化・LCR導入などを段階的に実施。
- 2019年:NSFR導入。
- 2023年:最終化パッケージが適用開始(コロナ禍で1年延期)。
- 2028年:アウトプットフロア完全発効。
6. 銀行に与える影響
(1) 資本コストの上昇
- 高品質な資本(普通株式)を多く要求されるため、資本調達コストが上昇しやすい。
- ROE圧迫要因となるが、健全性は向上しやすい。
(2) ビジネスモデルの変化
- 高リスク資産(トレーディング、証券化商品など)の縮小圧力がかかりやすい。
- 安定収益源としてリテールや取引銀行業務にシフトしやすい。
(3) 貸出姿勢への影響
- 規制強化により貸出余力が制約される懸念がある。
- 特に新興国では「銀行貸出の減少=経済成長抑制」の副作用が指摘される。
(4) システム安定性の向上
- 金融危機への耐性が大幅に改善。
- パンデミックや市場ショックに対しても資本・流動性を通じて耐性を発揮しやすくなった。
7. 評価と課題
バーゼルIIIの導入により、金融システム全体の安全性は向上しました。リーマンショック以降に最初に発生したG-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)の破綻事例となったクレディ・スイスの場合も、AT1資本が損失を吸収することで、同グループの銀行・決済業務は問題なく継続し、グローバルな金融システムに悪影響を与えることなく、UBSとの経営統合に進むことができました。このように、バーゼルIII銀行規制は、銀行破綻リスクの低減、市場の信頼感回復に寄与したことは明らかです。
一方で、移行期間の間には、地域ごとに導入時期や厳格度に差があるため、「規制のゆがみ(規制アービトラージ)」が生じやすいといった懸念が持たれた時期もありました。ただし、こうした懸念はバーゼルIII規制適用の最終化により、従来より薄まったと考えられます。
金融商品やサービスは、常に進化し続けています。このため、将来においてこれまで想定していなかったリスクが金融システムを脅かす可能性は、常に存在しています。そうした意味で、銀行規制の進化にはゴールはなく、今後も新たな課題に対応するためのルールが作られていくことになります。