AT1証券のベイルイン・トリガーの解説(3) -邦銀AT1債のベイルイン制度・リスク-
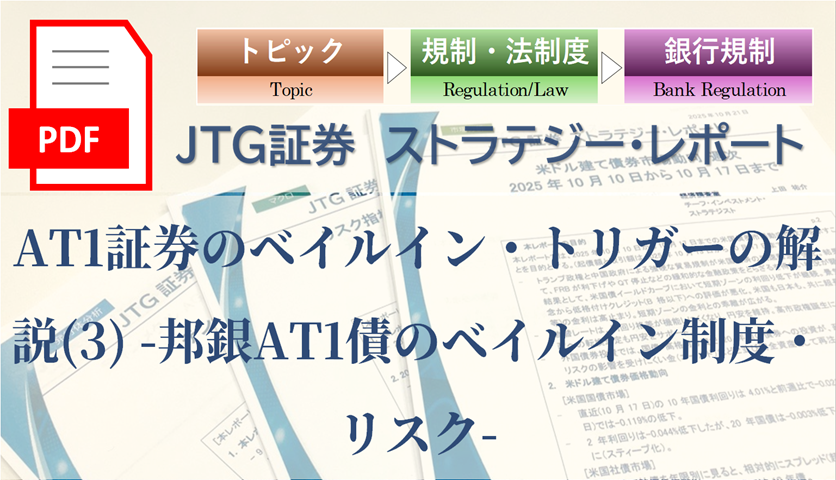
本レポートでは、日本における邦銀AT1債のベイルインに関連した規制上の評価点や、制度に関連した税務リスクなどについて解説する。
日本のAT1債のベイルイン関連規制
- 日本のAT1債などを用いた損失吸収は、すべて契約型アプローチ。
- 国内銀行が発行するAT1債の契約条件には、定量型と定性型の両方のトリガー条件が明記されている。
- 邦銀AT1債の定量的トリガー;一般に「連結CET1比率が5.125%を下回った場合」がトリガー。規制上は株式転換も可能だが、 MUFGなどの契約条項では、ほぼ額面減損と記載(ただし資本回復時の書き戻し条項あり)
- 邦銀AT1債の定性的トリガー(PONV);預金保険法126条の2第1項第2号に基づき「特定第二号措置」適用と認定された場合にトリガー。 定性的トリガー時には、AT1債の元本が即時かつ恒久的に全額償却。日本のPONVトリガーは自己資本比率にかかわらず発動可能 (CET1比率が5.125%を上回っていても当局判断でPONVの発動可能性あり)
- 邦銀AT1債では、クレディ・スイスと同様の、「株主の充分な減損負担なしに、先にAT1債が減損する(ゴーイング・コンサーン・イベント)」が制度上可能。
- 株主が損失負担する場合にも、時点のズレとして、PONV条項によりAT1債は銀行持株会社の法的倒産手続き開始前に消滅する可能性がある。
日本に特有の「破綻前」公的資金注入制度
- 日本の場合には、金融危機を回避するために、破綻に至っていない銀行に対して、予防的に公的資金を注入する法制(預金保険法第102条の2第1号)が存在。(りそな銀行に適用実績あり)
- 国内の大手銀行の経営が悪化した場合に、危機の予防目的で公的資金が注入されるのであれば、金融危機も当該銀行の経営破綻も発生しないことになり、AT1債のベイルインも回避されうる →「邦銀AT1債投資に特有で、他国制度に無い、独自の安定化要因」


