AT1証券のベイルイン・トリガーの解説(1) -各国規制比較-
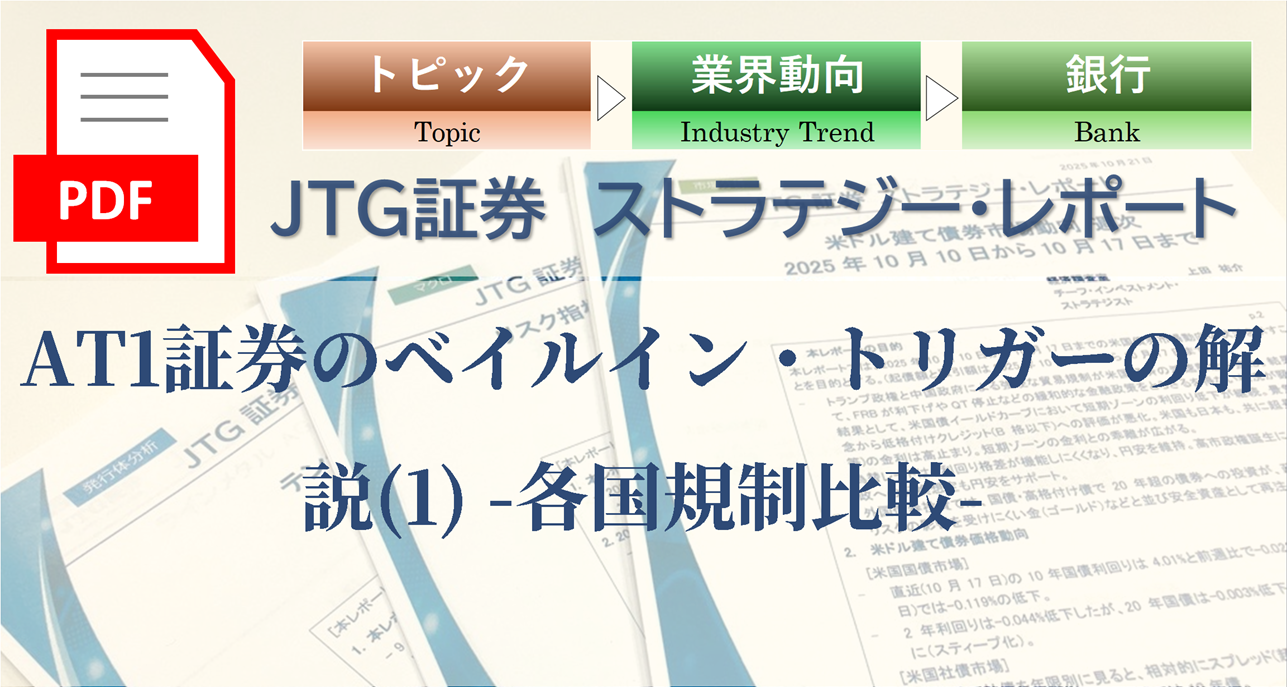
AT1証券投資におけるベイルイン・リスク(普通株式転換または額面の一部/全部の減額)を、各国・地域で異なる制度面から明らかにする。
AT1証券投資における問題意識
- 2023年のクレディ・スイスのように、銀行がそのまま経営を続ける中で、株主の損失より先に、AT1証券のみが先行して損失を吸収する状況が発生する「ゴーイング・コンサーン・イベント」は、どのような場合に生じ得るのか?
AT1証券のベイルインに関連した制度設計の論点別比較
- AT1証券にベイルインが生ずる2種類のトリガー;
- 定量的トリガー : CET1比率が5.125%/7%以下など
- 定性的トリガー :監督当局による実質破綻認定(PONV)
- 制度設計を比較したポイント;
- 法定型か、契約型か 法定型の場合、目論見書には契約条項として記載されない。契約型の場合は条項として明記
- 定量的トリガーの有無
- 定性的トリガー(PONV)の有無
- ベイルイン時の損失吸収手段(制度上の規定)
- AT1証券の単独減損(ゴーン・コンサーン・イベント)の有無
- 予防的な破綻前資本注入の可能性
- AT1資本の発行形態
AT1証券のベイルイン制度と潜在リスクのまとめ
- 最も容易にAT1証券の単独ベイルインが発生:スイス(UBS)
- ベイルインが最も制度的に抑制:日本(破綻前資本注入可)
- 制度の透明性が高い : アメリカ、カナダ(ただし税務リスクあり)
- 単独ベイルインは回避されやすいが、制度面の不確実性が残る: EU、英国


